ライフステージ別 血友病とのつきあい方乳幼児期(幼児/保育園/幼稚園)
監修
聖マリアンナ医科大学 小児科 長江 千愛 先生
乳児期は心身の発達が盛んで、視覚、聴覚、嗅覚などが発達してさまざまなことに興味をもつようになります。
幼児期になるとさらに活発に行動するようになり、子ども同士で外で遊ぶ機会も増えます。
このような時期は、保護者の方が出血予防のために家庭内での環境を整えたり、出血時の対応を身につけることが重要です。
しっかり観察し、受診タイミングを見逃さないことが重要
目に見えない出血が起きたら、保護者がなるべく早く発見することが大切です。出血すると腫れたり熱をもったりするほか、動きや行動に変化があらわれます。
しっかり観察し、受診タイミングを見逃さないようにしましょう。
■乳幼児期によくみられる出血
- ● 触ろうとすると嫌がる、手を払いのける
- ● 手足や関節を動かすと泣く
- ● 立ったり、走っていたりしていたのが急に座って遊びはじめる
- ● 歩き方がいつもと違う
- ● 食欲や哺乳力が低下し、気持ち悪がっている
- ● 顔色が悪く元気がない など

- 小島賢一:“18 幼稚園、学校、職場と自分の家庭を目指して” はじめてでも安心 血友病の診療マニュアル
- 宮川義隆ほか編 初版 医薬ジャーナル社:247, 2017
- 小倉妙美ほか:“Ⅱ.診断 1.臨床症状” みんなに役立つ血友病の基礎と臨床
- 白幡聡ほか編 改訂3版 医薬ジャーナル社:112-116, 2016
出血予防のために生活環境をひと工夫
つかまり立ちの時期は転びやすく、歩くようになってもはじめのうちはとても不安定です。生活環境をちょっと工夫することで、出血予防につながります。
おもちゃの上に座ったり、踏んだりしてけがをしないように、お部屋の片づけをこまめに行うようにしましょう。
■出血を予防するための生活の工夫
- ● 衣類にキルティングやパッドなどを縫い付けて二重にする
- ● ベビーカーにタオルなどを巻いて保護する など
- ● フロアマットなどを敷く
- ● 家具の角にカバーをつける
- ● サイズの合った靴を選ぶ
- ● クッション性のある靴や安定感のある靴を選ぶ

- 足利朋子ほか:“17 こどもへの病気の説明” はじめてでも安心 血友病の診療マニュアル
- 宮川義隆ほか編 初版 医薬ジャーナル社:237, 2017
自分の歯と長くつきあうために大切な口腔ケア
これからの長い人生を自分の歯で過ごすためにも、乳歯が生えたら歯みがきを開始しましょう。口腔内出血の予防のためにも口腔ケアは大切です。
■乳幼児期の口腔ケア
- ● はじめは保護者の方が歯みがきをしてあげましょう。
- ● 規則的な食事習慣を身につけさせましょう。
(ダラダラと食べる習慣は虫歯の原因に) - ● 定期的に歯科検診を受けましょう。

- 松本宏之:“13 抜歯の悩み” はじめてでも安心 血友病の診療マニュアル 宮川義隆ほか編 初版 医薬ジャーナル社:192, 2017
保育園、幼稚園との連携で早期発見、早期治療を
保育園や幼稚園に通うときは、血友病であることを園に伝えた方がよいでしょう。園での生活の中で、歩き方や行動に変化があったり、転倒やけが、頭をぶつけたときは連絡をくれるようお願いしておくと、出血の早期発見、早期治療につながります。
■保育園や幼稚園に伝えておきたいこと
- ● 関節に出血をすると関節が腫れて痛がる
- ● 打ち身であざができやすい
- ● 血が出たら止まりにくい など
- ● 緊急連絡先(保護者や主治医など)
- ● 出血が疑われる場合の症状
- ● 出血時のRICE(ライス:安静、冷却、圧迫、挙上) など
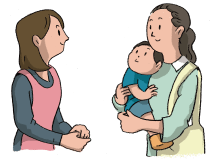
- 足利朋子ほか:“17 こどもへの病気の説明” はじめてでも安心 血友病の診療マニュアル
- 宮川義隆ほか編 初版 医薬ジャーナル社:242, 2017
家庭療法では成功体験を積み重ねることが大切
最近では、家庭での補充療法(家庭療法)を始める時期が早まっていて、2歳前後で始めるというケースも少なくありません。
保育園や幼稚園に通う頃までに、家庭療法や定期補充療法(定期投与)が行えるようになっていると、患者であるお子さんは制限なくさまざまな遊びができますし、保護者だけでなく保育園、幼稚園の安心材料にもなるでしょう。
■治療へのモチベーションを保つためのコミュニケーション
- ● 必要以上に怖がらせないよう、笑顔や優しい目で見守る
- ● 注射のときにアニメーションを見せるなど、気をそらす
- ● 注射が終わったら、スキンシップや言葉でがんばったことをほめる など

- 吉川喜美枝:Frontiers in Haemophilia 6(1) 33, 2019
- 小島賢一:“18 幼稚園、学校、職場と自分の家庭を目指して” はじめてでも安心 血友病の診療マニュアル
- 宮川義隆ほか編 初版 医薬ジャーナル社:245, 2017
